痛みや関節可動域制限がメインとなる疾患、それが五十肩です。
この五十肩は俗称であり、正式名称は肩関節周囲炎といいます。
今回はそんな肩関節周囲炎で行う評価・診断方法などについて紹介していきましょう!
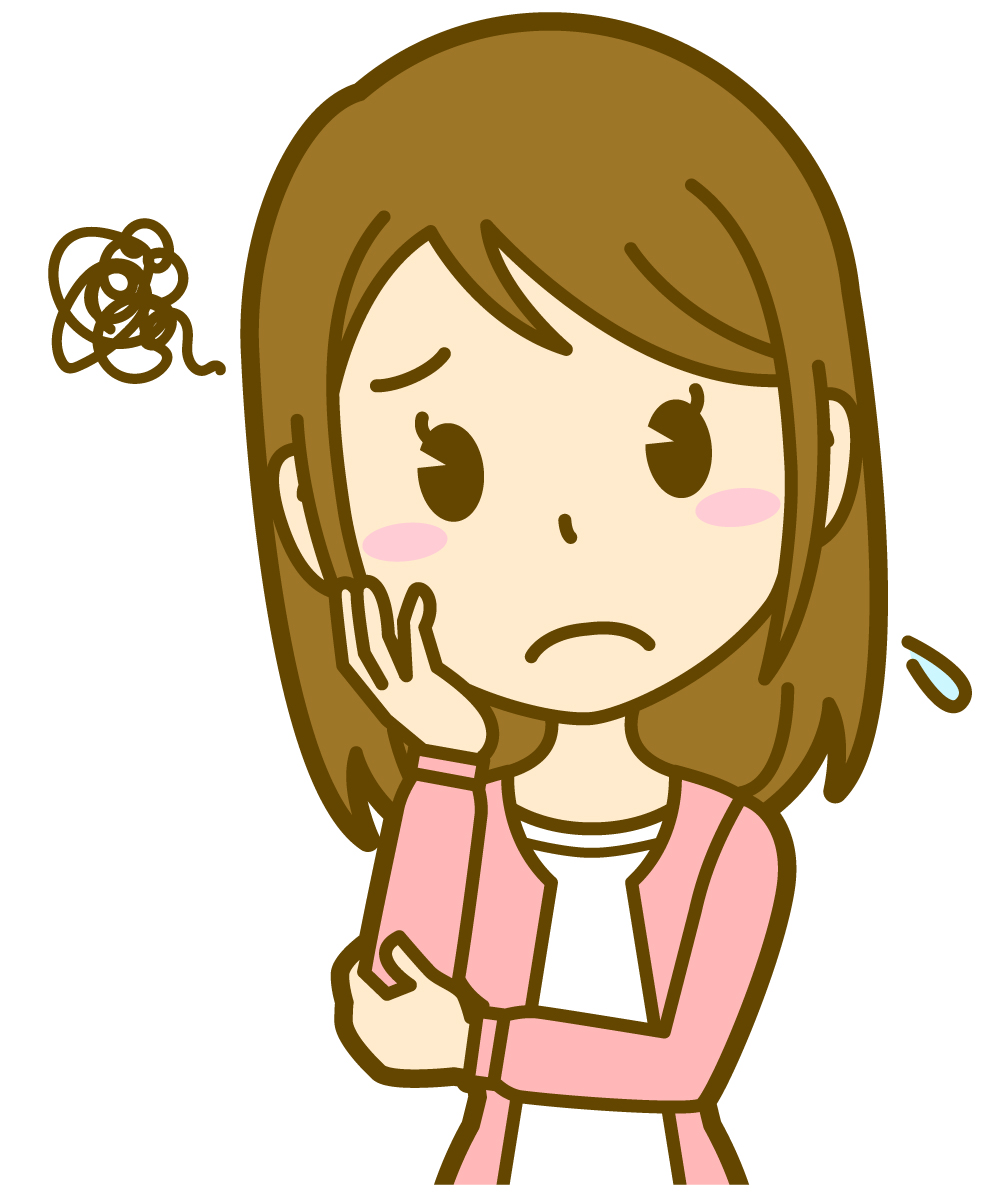 女性
女性五十肩の診察って痛いのかしら?



そもそもどんなところを診ていくの?



肩の動きを診るだけなんじゃないの?
などなど様々な悩み・疑問の解消をしていく記事となっています。
また、人体について興味がある方などもぜひ参考にどうぞ!



肩関節周囲炎の病態や症状を先に知りたい方はこちらの記事も参考にどうぞ!


診断時に行う内容について


診断時には様々なテストや聴取を行います。
その中でも特に行う内容について紹介していきます!
問診で肩の経過と具体性をチェック!
問診ではいつからか?どこからか?どのようにすると痛いか?きっかけは何なのか?など様々な観点から患者さんの状態を把握していくことを中心に行います。
本当に五十肩なのか?他の疾患から関連して痛みが出てきているんじゃないのか?など、問診している医師や理学療法士は考えながら聞いていくのです。
この問診で大切なのは、患者さんの状態を把握するだけでなく、患者さんの職業や背景のどこからきっかけがあるのかを追究していく必要性があり、原因を発見するにはとても大事なコミュニケーションとなります。
そのため、医師や理学療法士から色々聞かれますが、それは原因を探るために行っているものなので、問診には可能な範囲でしっかり問診に答えましょう!
視診にて腫れや変形などを確認!
基本的に五十肩の場合は肩の表面に炎症症状などは見つかりませんが、どちらかというと五十肩以外の疾患の可能性を減らすために行うようなものです。
炎症があるのか?変形が存在するのか?骨折していないか?
などなどを考慮して視診を行っていきます。
また、左右の肩の高さを比較してみたり、筋肉の萎縮の程度をみたりもします。
手を挙げてもらった時の肩甲骨の動きであったり、角度もこの時点で確認することもあるでしょう。
そのため、問診に続いて必ず行うのがこの視診なのです。
動作による角度や痛みの度合いを追及!
動作による追及、つまり肩を自力で動かしてもらって原因や問題を発見するのがこの診断のポイントです。
手を後頭部に回したときにどの角度が制限されているのか?
後ろポケットに手を回したときにどこまでの高さまで上げられるのか?
などのように関節の動かし方から症状の度合いを確認し、痛みも同時にみていきます。
この検査では原因を発見というよりも、症状の度合いを確認し、軽症か重症かを診ていくのが特徴です。
動作の確認はリハビリテーションでも行いますが、医師による確認もすることがあります。
評価で具体的な原因部位の確認と治療方針を決定!


ここでは主にどんなテストや検査を行っていくかを紹介していきます!
ただ、関節を計測するだけでなく、どこの筋力を測定しているかなどをかいつまんで説明しますね!
関節可動域測定による現状と原因を追究!
関節可動域を測る理由は単純に角度がどれくらいかを測るためのものではありません。
関節可動域測定で大事なのは、その角度からどこの関節に問題が生じているか?
もしくはどのタイミングで痛みが引き起こされるのかなどといった目に見えない部分を探るためとなります。
また、上がった角度だけでなくどのようにその角度まで上げたのかというのは重要で正しい動かし方で完成させているのかということも一つのポイントともなるのが特徴です。
そのため、単純に角度を測るだけでなく、痛みや動かし方などの細かい部分にも焦点を当てているのがこの検査のポイントとなります。
筋力測定にてインナーマッスルなどの弱い部位を特定する
筋力検査では主にインナーマッスルの程度をを確認していくのメインとなります。
基本的にアウターマッスルである
上腕二頭筋などは筋力が下がらず、どちらかというとインナーマッスルである棘下筋や肩甲下筋、棘上筋などの筋力をテストして大まかに把握していきます。
五十肩の場合では、インナーマッスルの低下によるものが多く、肩甲上腕関節の筋力だけでなく肩甲胸郭関節に関わる前鋸筋などの筋力や力が入るかを確認していくのが特徴です。



インナーマッスルについて知りたい方はこちらの記事も参考にどうぞ!
アプレースクラッチテストによる能力テスト
アプレースクラッチテストは結滞・結髪動作といった首の付け根に上から触ったり、腰に手を回して高さがどれくらいまで持っていけるのかを確認する能力テストとなります。
このテストの特徴は単純に動作を行ってできるかというわけではなく、この動作ができないことによる生活への支障の程度を把握することが可能です。
たとえば結髪動作であるならば、髪を結んだり、クシでといたりするのにも関係してきます。お風呂での洗髪もそうですね。
結滞動作では、下着の着脱の不便さ、トイレでのお尻ふきなどといった日常場面によるさりげない動作に関与してきます。
このように、ただ単純にテストをしているわけでなく、それぞれが生活のどの部分に支障を与えているのかを検証するのがこのアプレースクラッチテストの役目です。
指椎間距離測定で結滞動作の可否を診る
アプレースクラッチテストの結滞動作のみの測定となります。
ただし、このテストでは結滞動作による関節の柔らかさを検証しており、どこからどこまで届いたかを数値で出すのが特徴です。
基本的に結滞動作の行い方は変わりませんが、親指を当てた位置が頸椎とどれくらい距離が離れているかを確認していくのがポイントとなります。
そのため、運動前や運動後にどれくらい改善されたのかを測定するのには有用でありますが、一時的なものなので数ヶ月かけてどのくらい関節の動きを取り戻したかについて患者さんに説明するためには必要となります。
ヤーガソンテストで上腕二頭筋長頭炎の有無を確認
ヤーガソンテストは主に上腕二頭筋長頭腱炎の有無を確認していくのが特徴です。
まず、患者さんに椅子に腰かけていただき、テストする人は検査する腕側に立ちます。
患者さんに直角に肘をまげていただき、テストする人は肘がうごかないように固定します。
その状態で患者さんは腕を外にひねってもらい、痛みが出たら陽性となるのがこのヤーガソンテストです。
【参考文献】
編集/石川齊,武富由雄.図解理学療法技術ガイド 理学療法臨床の場で必ず役立つ実践のすべて 第2版.文光堂.2007.738-739P
監修/富士武史,共著/河村廣幸,小柳磨毅,淵岡聡.ここがポイント!整形外科疾患の理学療法改訂第2版.金原出版株式会社.2012.98-101P
著者/松澤正,江口勝彦.理学療法評価学改訂第4版.金原出版株式会社.2012.89P
【結論】肩の診断・評価は意外と複雑!


お疲れ様でした!最後まで読んでいただきありがとうございます!



わりと数値しか見るだけじゃないんですねー
初めて知りましたー


そうですね。テストで数値や結果はもちろん大事なのですが、やはり見えない部分に対する観点にも焦点を当てるのは非常に大事となります。



動作や痛みのタイミングとかですね!


そうです!見えない部分だけあってはっきりと原因を見つけるのは難しいですが、テストを複数行い、その結果から総合的に判断するのでその材料としては非常に有用となるので覚えておきましょう!



分かりました!参考にさせていただきます!
それでは今日はこの辺で!


お疲れ様でした!
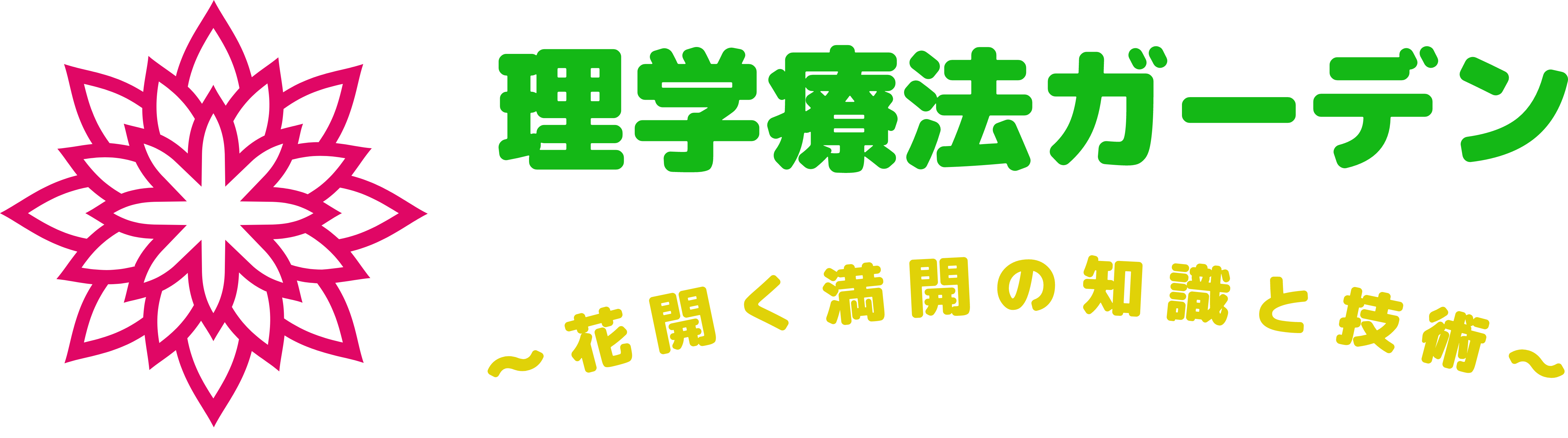
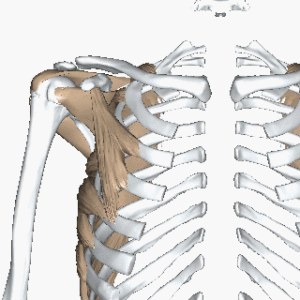
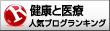

コメント